30年後のチェルノブイリが教える真実
29.04.2016

Photo: world-nuclear
廃炉や核汚染した原子炉の処理は一般に30-40年を要すると言われているが、それは甘い見通しであることをチェルノブイリが教えてくれる。事故から30年後に当たる今日でも、ベラルーシ国境を越える広範囲の地域が汚染されたままである。AP電によれば原子炉から45km離れた農場の牛乳が国内規制値の10倍の放射能レベルに達する。
事故から10年後の1996年にIAEAは黒鉛型原子炉から放出された放射性物質は広島型原爆の400倍以上と推定した。周辺の地域では苔や菌がセシウムに汚染され、プルームは1,600km離れたノルウエーに達した。住民が避難した後には野生の動物が繁殖したが、放射線の影響でこの地域の鳥類は脳が5%小さいという。
グリーンピースの10年前の調査では癌発生は250,000件に達しそのうち死にいいたる重篤なケースは93,000例であった。これから推定される被曝による死亡は60,000人、今後ウクライナとベラルーシで140,000人が癌発生のリスクがあると推定された。一方、国連の調査では癌で亡くなった人の総計は4,000人としたが正確な被害者数の統計が困難であった。
チェルノブイリ事故は原子炉が従来の考え方を根本的に変えるほどの人的被害と環境汚染リスクを原子力利用が持つことを認識させることとなった。またこの事故により経済的に疲弊しい犠牲を強いられた軍人の士気の低下はソ連崩壊を早めた。4基が危機的状況に陥りそのうち3基が炉心溶融した福島原発がチェルノブイリに比較されるが、被害が甚大で収束が困難を極めたチェルノブイリは人類の脳裏に深く刻まれることとなった。
安全性にリスクを抱えていることに加えて、原子力のもう一つの問題である核汚染物質の処分法が決まらないことによって、再生可能エネルギーへの動きが活発化した。また燃料採掘と加工、処分で温室効果ガスを含めると原子力の優位性がなくなった。9/11テロや福島事故を受けて建設基準が厳しくなり、設計が複雑化するとコストが高騰し新規建設は遅れが目立つようになった。未来のエネルギー源としての原子力利用に暗い影が指しているが、きっかけとなったのはチェルノブイリ事故であった。
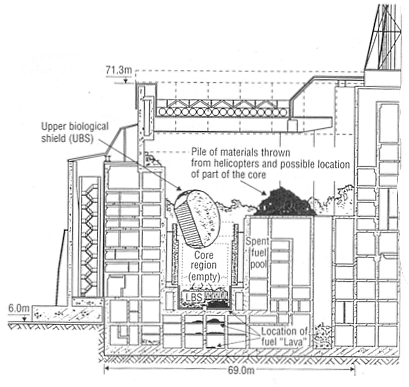
Credit: world-nuclear
実際、過去10年にわたり研究が進み放射線が動植物に与える影響が明らかになった。低線量でも電離放射線被曝効果が無視できないことがわかり、日常的な摂取により体内に蓄積された核汚染物質が事故周辺地域の動植物分布に影響を与えることも明らかになった。放射線の被曝でDNAが損傷し癌発生が増えるのである。
放射線が生体に及ぼす効果は被曝者の追跡調査によって調べることしかできない。チェルノブイリでは事故後の情報隠蔽により住民の避難や農作物の破棄が遅れた目、このような大規模な被曝者を出した。その全ての追跡調査で癌発生に代表される健康被害が明らかにされた。
しかしそれでも福島事故の初期の段階で炉心溶融や汚染の予測は隠蔽された。欧米のメデイアが福島事故で敏感に反応し深刻さをいち早く報道した理由はチェルノブイリの悲惨な経験を生かそうとしたからだ。未だに福島廃炉は30-40年で収束し避難住民は帰還できる印象を国も電力会社も発信し続ける。
しかし30年後のチェルノブイリが何も変わらないのと同様に、30年後に放射線強度が1/2に減少したところで、格納容器に近づくことすら不可能である。水棺法のリスクに目を瞑るとしても安全な作業には写真のような遮蔽い建物の中で作業するべきだ。除染が汚染土の「移動」に過ぎず、それすらできない地域への住民の30年後の帰還が非現実的なことは目に見えている。廃炉が困難である事実と財政的な負の遺産を若い世代に背負わせることを国民に知らせるべきだ。それが30年後のチェルノブイリからの警告である。
