気象予報技術の進歩
28.01.2019
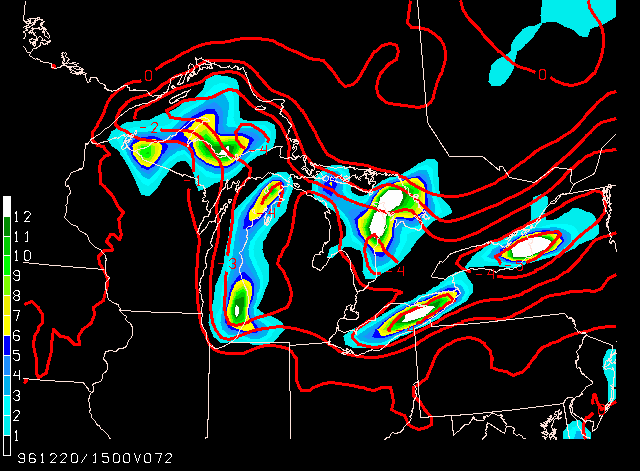
Credit: weather.gov
ペンシルベニア州立大学とマサチューセッツ工科大学の地球科学研究チームは、天気予報技術の進歩を解説し、予測の正確さが改良されていることをハリケーン予報で実証した。論文は気象予測技術がどのようにして実現したかを説明した上で、将来実現可能な技術を展望した。(Alley et al., Science online Jan. 25, 2019)。
気象予測が改善された背景
観測、数値モデリング、およびデータ同化の重要な進歩により、予測技術の向上がもたらされた。特に大気や地表の衛星によるリモートセンシングによる観測手法の改善で、貴重な地球規模の膨大なビッグデータが1日に何度も提供される。計算機能力も飛躍的に向上したため、大気物理学とダイナミクスの理解が進み、より正確な数値予測モデルが可能になった。
観測データは多くの場合、空間的に不完全で不確実なので、常に大気の状態を正確に知ることはできないことで、予測の誤差が生じる。気象モデルを長期にわたって観測データと矛盾しないように調整することによって、予測精度は、大幅に向上する。このためには、4次元変分法、アンサンブルカルマンフィルタ、またはハイブリッド手法が使われ、気象予測に革命をもたらした。
長期予測精度は気象モデルの初期条件(観測データ)入力に対する感度に依存する。初期条件に対する感度は時空間で大きく異なるため、原則として、2週間を超えて天気の詳細を正確に予測することは難しいが、最新の天気予報システムでは季節的、年毎、あるいはそれ以上の時間スケールで予測が可能である。例えば、マッデン - ジュリアン振動(MJO)(注1)は東方向に動く雨、風、雲、気圧、夏季モンスーンの発達と消滅に影響を与え、30~90日にわたる周期で熱帯地方周辺の農業を左右する。最新の気象予測モデルで、最大5週間までMJO現象の予測が可能になった。
(注1)マッデン・ジュリアン振動(Madden Julian Oscillation:MJO)は、熱帯赤道域上空で対流活動が活発な領域(大気循環場)が約1~2か月かけて東に進んでいく現象。その周期は30-60日程度で、大気振動現象のひとつである。
予測技術の改善と並行して、気象データ通信環境が改善された結果、詳細かつ正確な情報が市民にタイムリーに流れるようになった。ほんの数10年前、朝の新聞や夕方のニュースでしか最新の天気予報が得られなかったが、今日では、スマートフォンでどこにいても、地理的に的を絞った天気情報を入手できる。
詳細な沿岸形態に対応したハリケーンや夏季の海氷喪失の予測に加えて、ハリケーンの規模と災害警報や正確な海氷予測などが可能になった。下図はNOAA国立ハリケーンセンター(NHC)のデータから得られた1海里(1 nmi = 1.852 km)内の予報誤差をグラフにしたもので、ハリケーンの予測誤差がここ数10年で急激に減少したことを示している。
Credit: Science
研究チームによれば、予測精度の改善で最も重要なのは、計算機ハードウェアとソフトウェアの進歩だという。将来の予測は単なる雨や雪を予測するだけではなく、森林火災の移動経路や、北極で氷がどれだけ溶けるか、海面がどれだけ上がるかなども含まれると期待されている。
計算能力と気象モデルが向上することで予測精度はさらに向上する一方、天気予報のコストも増大するので、政府機関と民間機関の両方による投資が鍵となる。異なる国間でのデータ共有も重要で正確なビッグデータは、すべての人に利益をもたらす。気象データの取得に国際ネットワークが必要であり、ビッグデータを共有すれば地球規模での気象予報が可能になる。
